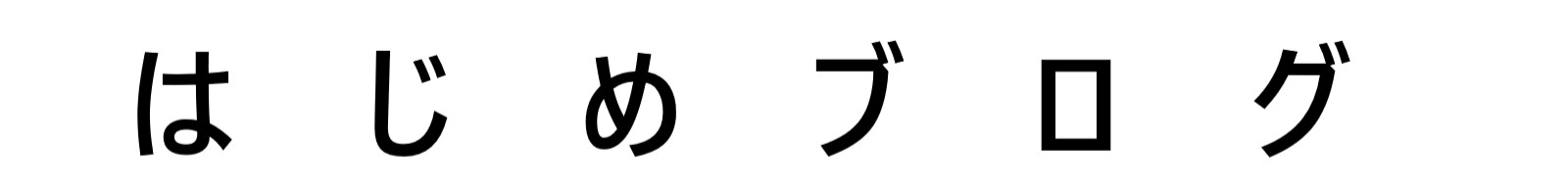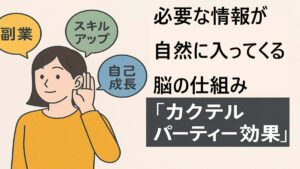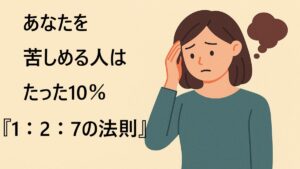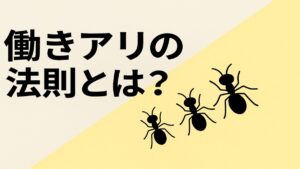こんにちは、はじめです。
最近、学習関連やCMなどで耳することも多くなった、「認知能力」と「非認知能力」。
これらは、私たちの成長や社会生活においてとても重要な2つの力です。
それぞれどんな意味を持ち、どんな違いがあるのかを分かりやすく解説します。
認知能力とは?
認知能力とは、主に「知覚」「思考」「記憶」「言語」など、論理的・知的な情報処理に関わる能力のことです。
たとえば、計算力や読解力、記憶力、判断力、言語能力などが該当します。
IQ(知能指数)やテストの点数など、数値で測定できる能力がこれにあたります。
認知能力の例
- 記憶力(物事を覚える力)
- 言語能力(言葉を理解し使う力)
- 判断力(状況を分析し決断する力)
- 計算力(数字を理解し計算する力)
- 遂行力(計画を立てて実行する力)
認知能力は、学校の勉強や資格試験、仕事の専門知識など、学力や知識の習得に直結するため、従来の教育現場で重視されてきました。
非認知能力とは?
非認知能力とは、テストなどで数値化することが難しい「人間的な力」や「内面的なスキル」を指します。
たとえば、目標に向かって努力する力、意欲、創造性、コミュニケーション力、自己管理力、忍耐力、協調性、感情のコントロールなどが含まれます。
非認知能力の例
- 目標を立てて粘り強く取り組む力
- 自分の感情をコントロールする力
- 他者と協力する力、思いやりや共感力
- 新しいアイデアを生み出す創造性
- 失敗しても立ち直る力や自己肯定感
非認知能力は、学力テストの点数やIQでは測れませんが、人生を豊かにし、社会で活躍するために欠かせない力として近年とても注目されています。
2つの能力の違いと関係
- 認知能力は「知識や論理的思考など、数値で測れる力」
- 非認知能力は「意欲や社会性、感情のコントロールなど、数値で測れない人間力」
この2つは独立しているわけではなく、相互に影響し合っています。
たとえば、自己管理力や忍耐力(非認知能力)が高いと、学習意欲や集中力が高まり、認知能力の向上にもつながります。
なぜ今、非認知能力が注目されているの?
社会や働き方が大きく変化する現代では、知識やスキルだけでなく、変化に適応し、他者と協力し、自分の感情をコントロールする力がますます重要になっています。
大学入試や就職活動でも、面接やグループディスカッションなどを通じて非認知能力が評価される場面が増えています。

まとめ
- 認知能力…数値で測れる知的な力(記憶力・計算力・言語力など)
- 非認知能力…数値で測れない人間的な力(意欲・協調性・感情コントロールなど)
どちらもバランスよく育てることが、これからの時代を生き抜くために大切です。
子どもだけでなく大人になってからも、日々の生活や仕事の中で、両方の力を意識して伸ばしていきましょう。